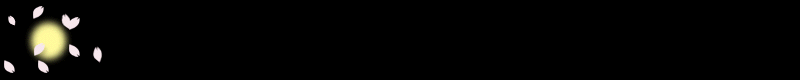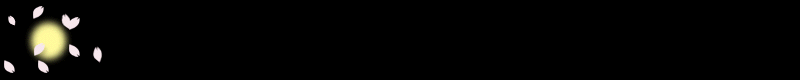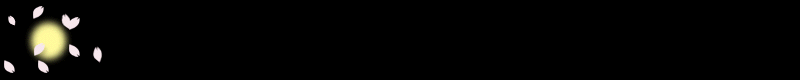それは夏の盛り。
龍神の神子とその八葉は白龍の力を召喚し、黒龍の瘴気を祓って、鬼の野望を潰えせしめた。
穢れが昇華された京は、晴れ渡った美しい青空で人々を包んでいる。
龍神様の加護だと人々は喜びあい、神と神子を称える声が街中に満ちていた。
それから数日後の事。
蘭は藤姫の離れの庭にたたずんでいた。
鬼に捕らわれていた彼女は、アクラムの消失により呪縛が解かれて自由になった。だが、蘭も含め現代人たちはまだ京にいた。
アクラムとの決戦後、白龍の媒介となったあかねも、黒龍の媒介となった蘭も疲れきっていた。特に、蘭は術によって精神的にも疲弊しており、二人の身体の調子が良くなるまで、藤姫の離れに引き続き世話になる事になったのだ。
最初は起き上がることも辛かった蘭だが、手厚い看護のおかげで、普通の生活に支障がないところまでは回復していた。もう、一人で外に出ることもできる。だが、兄が心配してあまり遠くまでは行かせてくれないので、こうして庭を眺めるのが蘭の数少ない楽しみのひとつだった。
藤。橘。夏椿。土御門邸の庭は幾種類もの花々が趣味良く配置され、盛りの花々が惜しげもなくその美しさを誇っている。それらはいつも蘭の心を和ませてくれる。
花の庭を蘭はゆっくりと歩いた。
だが、その歩みを留めるように、不意に強い風が巻き起こった。
彼女の長い髪が風に舞う。顔にかかった幾筋かを振り払いながら、何気なく空を見上げた蘭は、どくんと心臓が高鳴るのを感じた。
――――花嵐。
風に吹き上げられた花弁が、最後の輝きを放つように陽の光を受けてきらきらと空を舞っている。風はまたさらさらと清々しい音を立て、花の芳香を蘭の元に運ぶ。
蘭は吐息を漏らした。
自然はかくも美しいものを作り上げる。陰陽の気の理が整ったこの地は、今輝くばかりの美しさに彩られていた。
「…あ、蘭ちゃん!」
不意に明るい声が蘭の背後からかけられた。蘭が振り返ると、あかねが廊下に立って庭の彼女に向かって手を振っているのが見える。
蘭は風で身にまとわりついた花弁や埃を払い落とすと、あかねのいる廊下へ歩いていった。
「おはよう、あかねちゃん」
「おはよう。今日も庭を見てたの? そんなに気に入ってもらえて嬉しいって藤姫が言ってたよ」
蘭が柔らかく微笑む。
「そうなの。この庭はとても綺麗だわ。ずっと見ていても飽きないの」
「そっか。でも、立ちっ放しで大丈夫? 疲れるでしょ?」
「私はもう平気よ。出歩く事だってできるんだから」
「そうだね、本当に良かった。天真くんもこれで安心だね」
彼女の口から兄の名が出た途端、蘭の表情がかすかに揺れた。だが、本当にかすかな変化だったので、あかねは気付かなかった。
「そういえば、お兄ちゃんは…?」
「うん……」
蘭は単に変化を気付かれたくなくて尋ねたのだが、あかねは何故か難しい顔になった。
「今は藤姫の部屋にいるよ。頼久さんとか泰明さんも一緒」
蘭は小さく首を傾げた。
「何かあったの?」
「それがね…。最近、この辺りで変な事が起こってるんだって。別に悪い事ってわけじゃないんだけど」
「変なこと?」
「ここ数日、夜になるとあちこちで変わった事が起こるの。風なんて全然ない日に突風が吹いて、満開の花を散らしたり、どこからともなく地鳴りが聞こえてきたりね。被害が出てるわけじゃないんだけど、みんな気味悪がってるの」
「そうなの……」
蘭の表情が曇る。あかねは困ったように続けた。
「それで、天真くんがどうせする事ないから見回りをするって言い出したの」
「お兄ちゃんが…?」
「うん、武士団の人とかと一緒にね。あんまり不安が広がると、治安上も良くないし。その事を話し合ってるの」
「そうなんだ。あかねちゃんも藤姫の部屋に行くところなの?」
あかねが眉をしかめて、首を横に振る。
「私は首を突っ込むなって言われてるの。無謀な事するからって。天真くんこそ、すぐに無茶するところがあるから、心配なのに」
口を尖らせるあかねに、蘭は目を細めて笑う。
「ふふ。でも、さすがのお兄ちゃんもあかねちゃんには敵わないみたいね」
「え? そんな事ないよ」
「ううん。だってお兄ちゃん、私の言う事なんていつも聞かなかったけど、あかねちゃんの言う事は、結局はきいてるみたいじゃない?」
「そうかなあ」
あかねがかすかに赤くなりながら、照れ隠しのように髪をかきあげる。口では否定しつつも嬉しそうだ。
嬉しいだろう。恋人が自分を大切にしてくれてるという事なのだから。
「じゃあ、お兄ちゃんは当分忙しくなるね」
「そうだね。どこで起こるか分からないし。ここ付近でだけっていうのが救いだけど」
「何もかも良くなった訳じゃないのね……」
蘭がぽつりと呟く。その声音に含まれる悲哀に、あかねは慌てたように努めて明るい声を出した。
「でも、これからいい方向に進んでいくはずだよ。問題は残ってるけど、みんなで京の危機を乗り越えたんだもん」
蘭はふと微笑んだ。「みんなで」と言うところが彼女の優しさだ。
蘭は鬼として京を穢してきた。その過去を気にさせまいと彼女はいつも気遣ってくれる。
彼女は優しい。その優しさが蘭は本当に好きだった。
その後、蘭はあかねと別れて、通用口のほうへ向かっていた。
起き上がれるようになって以来、京の通りを散歩するのは彼女の日課だ。今日もそうしようとして、その途中で一人の男性と出くわした。
「おや、姫君お一人かい?」
「あ、友雅さん…」
にこりと微笑んだ彼に、蘭も会釈を返す。
彼は八葉の一人で、戦いの最中、何度か対峙したことがある。だが、おかしな事にこの邸に来てからは、ほとんど言葉を交わしていなかった。接点がないし、ひそかに聞いたところによると、女性との艶聞が絶えない彼を、兄が故意に遠ざけていたらしい。
だが、彼はそんな事は気にした様子もなく、蘭と会えばにこやかに挨拶をくれるし、いくつか小物を贈ってくれた事もある。そのため、彼にはどちらかと言えば良い感情を持っていた。
「こんにちは。来ていたんですね」
「ああ、姫君方にご挨拶にね」
軽い口調で答える彼を、蘭はちらりと見上げた。
「あなたも近頃起こっている変事のことで来たんですか?」
そう尋ねると、友雅の瞳に興味深げな色が浮かぶ。その視線は何とも言えず艶かしくて、蘭は兄が心配したのも少し分かるような気がした。
「藤姫や君の兄上はその怪異を止めたいと思っているようだね。私はどちらかと言えば興味を覚えているんだが」
「興味?」
「風を吹かせて花嵐を起こしたというじゃないか。何とも風流な怪異だと思わないかい?」
楽しそうな彼の様子に、蘭は呆気に取られた表情になる。
「でも…、怪異だわ。みな、怯えているんでしょう?」
「陰陽師の泰明殿が言うには、瞬間的に起こるだけで、跡も残らないようなささいなものだそうだ。害はないのだから、そういう不思議があるのも楽しいだろう。一度見てみたいものだね、その花嵐を」
蘭はしばらく沈黙した後、どこか自嘲気味な笑みを浮かべた。
「けれど、その花嵐は偽物でしょう? 本物には敵わない。私はさっき本当の花嵐を見たわ。美しかった…、泣きたくなるくらいに」
「…ふうん。君は天真とはあまり似ていないね。その風雅を解する繊細さで、ぜひ私と語り合ってほしいものだ」
友雅がそう言った時、彼の背後から足音が近づいてきた。
「蘭、…友雅?」
友雅が小さく肩をすくめる。蘭が彼の後ろに視線をやると、天真がそこに立っているのが見えた。
「邪魔が入ってしまったね。またいずれ、蘭殿」
囁くように言って、友雅は離れの奥に歩いていった。それを見送る蘭の横に、天真が慌てたように駆け寄ってくる。
「おい、友雅と話してたのか?」
「え、うん……」
「…変な事されなかったろうな?」
真面目な顔で蘭に詰め寄る天真に、蘭は呆れたような視線を返した。
「お兄ちゃん、失礼よ。ただ、近頃起こっているって言う変事について話してただけ」
「ああ、それか…」
とたんに天真が難しい顔になって、腕組みをする。そんな兄に蘭は笑いかけた。
「お兄ちゃん、見回りに行くんだってね。気をつけてね」
「ああ。…ところで蘭、出かけるのか?」
「うん。お散歩」
蘭が頷くと、天真は今度は渋い顔になる。
「あんまり一人で出歩かないほうがいいぞ。変な事件が起こってるんだから」
「うん…、ありがと。でも、すぐそこの通りを歩いてくるだけだから。それに、おかしな事が起こるのは夜だけなんでしょ?」
「まあな。そういや、聞こうと思ってたんだけど、お前いつも一人でどこに行ってるんだ?」
「ただ、その辺りをぶらぶらと歩いているだけよ。私、ゆっくりと京の町を歩いた事なかったから、それだけでとても楽しいの」
「あ、そう、か……」
天真の口調が歯切れの悪いものになる。蘭の今までの生活の話になると、彼はいつもそうなのだ。
「…じゃあ、ちょっと待ってくれるか? 俺も行くから」
そして、必ず埋め合わせをしようとする。
蘭は笑って、首を横に振った。
「いいよ。あかねちゃんから聞いたよ、忙しいんでしょ?」
「そんな事…。じゃあ、せめて誰かと…」
「みんな私みたいに暇じゃないもの。迷惑をかけたくないわ」
「でも……」
天真はまだ渋い顔だ。
きっと、本当は蘭を止めたいのだろう。だが、彼女に対する引け目がそれをさせない。彼のまっすぐな気質は、蘭と相対するときだけ、その形を歪める。
それは彼の優しさなのだろう。
「大丈夫だって。それじゃ、行ってくるね」
「…できるだけ、早く帰るんだぞ」
天真はそう言った。それしか言えなかった。
蘭は頷いて天真の横を通り抜けると、ひそかに苦い笑みを浮かべた。
――――その夜、また花嵐が起こった。次の夜も、また次の夜も。花嵐は続く。
|