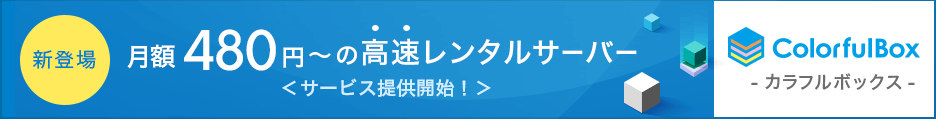東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花
主なしとて 春な忘れそ
友雅はやわらかな東風に髪をなびかせながら、ゆっくりとその荒れた庭をめぐっていた。
久方ぶりに奏でた篳篥(ひちりき)の音が、聞く者とてない邸に響き渡る。人への気遣いが存在しない、そのゆえに、笛の音は澄み切っていた。
やがて、彼は足を止める。
篳篥を下ろし、見上げた先には、見事な梅の花が咲き誇っている。
今年も、彼はこの梅を見に来た。
かの歌人と同じ運命をたどった、親友の代わりに。
友雅の口の端に、つと笑みがのぼる。
毎年、この梅を見るたびに感じていた切なさが、少しも湧き上がってこない。
自分が変わったからだ、と彼には分かっている。
叶わぬ恋に、その身を滅ぼした親友。
そんな気持ちが自分にも訪れたから。
友雅は静かに目を閉じる。
いや、始めから分かっていたのかもしれない。
だが、恐らく、そうなるまでに、自分に一言も打ち明けぬまま去っていった彼が憎かったのだろう。打ち明けたところで、あの頃の友雅は一笑に付した、そう分かっていても。
そんな不条理な気持ちを、情熱とともに置いてきた、昔日の思い出。
なんと愚かで、身勝手だったことか。
そして、なんと情熱に満ちた、愛しい日々であったのか。
友雅は目を開け、花の連なりに愛しげに手を伸ばした。
「忘れないよ、この梅も、その主も。そして、主の恋もね」
友雅は再び篳篥を口唇に当て、澄んだ音を響かせながら歩き去っていった。
―― 了 ――
|